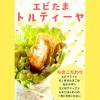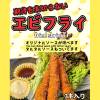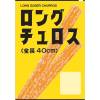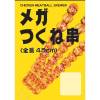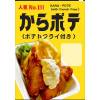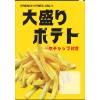織部ヒルズの住人たち – 株式会社結彩の蔵
プロに寄り添う心強い伴走者 株式会社結彩の蔵
作り手、売り手、担い手が一堂に会す織部ヒルズに、産地問屋として17年前から根を張る株式会社 結彩(ゆうさい)の蔵。丁寧なヒアリングを行い、二万種類以上ある器の中から、飲食店が求める最適の器を探し出す、飲食店の伴走者です。
統括本部長の加藤景治さんは、どんぶり鉢の産地としても知られる土岐市駄知町の出身。身近な家族や親戚の多くが陶磁器に関わる仕事をしていたことで、幼い頃から「器の世界」は生活の延長線上にありました。
ブライダルギフトが隆盛を極めていたころ、陶磁器を扱う商社に就職し、営業としてギフト需要を肌で感じながら、器づくりの現場を見て歩きます。
企画、製造、流通、トレンドの変化など、目まぐるしい産業構造の中、どんな器が喜ばれるのか。違いを見極める眼と、柔軟に提案をつくるセンスを養いました。
今回は、その加藤さんに結彩の蔵についてお話しをお伺いしました。

お客様にとって“正解”は一つじゃない
2008年創業の結彩の蔵。「結」は“人と人をつなぐ”、「彩」は“食卓を彩る器の力”。器という道具を通じて、人と食、人と人とが豊かに結ばれていくようにという願いが込められています。
メーカーの既製品だけでなく、飲食店などのお客さまの要望に応じてオリジナル商品も手がけています。
「こちらが“これは絶対に良い”と思って選んだ商品でも、それが売れるとは限りません。今は、飲食業界の中でも料理人が食器を選ぶとは限らず、空間コーディネーターやプロデューサーが関わることも多い。店舗ごとのカラーや空間演出に器が合っているかどうか、トレンドや好みを的確に見極めないといけないんです」
そんなニーズに応えるべく、結彩の蔵は2万点以上の器を揃えたショールームを違う場所に持っているといいます。
ゼロから揃える方もいますが、多くの方はすでに使っている器があります。そのうえで、料理やコンセプトに合わせて新たな器を選んでいただくと、イメージも湧きやすいので、時間が許すのであればショールームにも来てもらえれば、と言います。
人気商品があるのかをたずねたところ、加藤さんはこう答えました。
「“売れ筋”というものは、実際にはほとんど存在しないのです。だからこそ、一件一件のお客様と丁寧に向き合い応える。そこに価値があると思っています」
“どこにもない”ではなく、“その店や人にとってちょうどいい”こと。その一皿を見つけ出す手助けができることが、結彩の蔵の本領です。

陶器市では蔵出しの宝探しを
そんな結彩の蔵が、陶器市で行うのは、店舗を開放した蔵出し市です。
業務用中心に展開している商品群の中から、廃盤品や昔のレアものなどを、特別価格で提供する予定です。
また、どんぶりや鉢といった食器の品揃えには定評があるので、飲食店関係者はもちろん、家庭でちょっと本格的な器を探している人におススメです。
器は、作られた用途や目的がはっきりしていますが、どんな料理をのせるか、どんな場面で使うかを想像することが大切です。
使うために作られた器。料理を引き立て、使い手に長く寄り添う、そんな実用性と美しさを兼ね備えている無数の器の中から、それぞれに合った最適な器を探してくれる結彩の蔵は、まさに最強のパートナーです。
これからはじめる人を全力で応援する
加藤さんは、これから飲食店を始めたいという人にぜひ来てほしいと言います。
「飲食店の開業って、簡単ではありません。準備や資金面、デザイン、メニュー構成…いろいろな背景があると思います。でもだからこそ、相談してもらえれば、一緒に考えることができる。器はあくまで手段ですが、それがきっかけとなって、前向きな一歩を踏み出す応援ができれば幸いです」
器を超えて、人の想いに歩幅を合わせながら並走する。その真摯な姿勢に、加藤さんの人柄と企業の温度が表れています。
あなたに合う器を、一緒に探します
これが結彩の蔵の原点です。一方通行ではない、真摯な対話の姿勢。何万点と並ぶ器の中から、ぴたりと合う“その一皿”を探し出す、その手間を惜しまず、どんなに小さな希望にも耳を傾ける。仕事のすべてに、“プロを支える誇り”が込められています。
今年の陶器市でも、「特別な器」との出会いが待っているはずです。
はじめる人も、迷っている人も、ぜひ一度、結彩の蔵の扉をたたいてみてください。
器選び以上の価値が待っている、あなたの「これから」に寄り添ってくれる場所。器を通じて、前に進む力がきっと得られるに違いありません。
株式会社結彩の蔵
住所:岐阜県土岐市泉北山町4-3(織部ヒルズ内)
公式HP:https://www.yusainokura.jp/
※陶器市期間中の詳細イベント情報は、織部ヒルズ公式Instagram・HPでも随時更新中!